【初学者目線で】量子力学の教科書選び
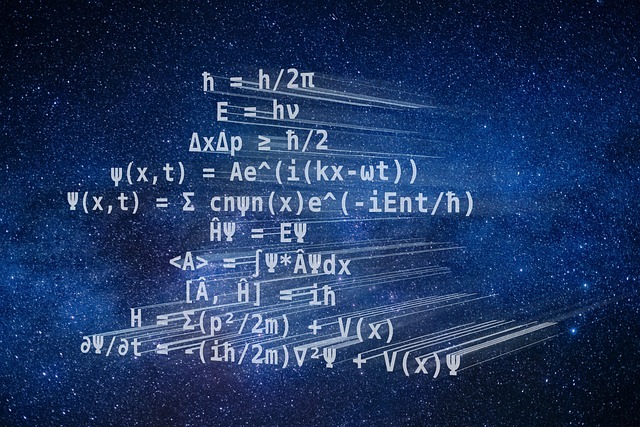
量子力学と相対性理論は、現代物理の双璧を成すとても魅力的な分野です。物理系を志望する新入生や意欲的な高校生なら誰でも焦がれる分野でしょう。
しかし、どちらも内容は高校範囲と比べて飛躍的に難解です。また独習をする際には、いったいどの教科書をやればいいのか困ると思います。
今回は、そんな方たちに向けて、筆者が学部1年生の時に図書館で読んだり自分で買ったりした量子力学の教科書の紹介をしたいと思います。
筆者自身まだこの分野を学んでいる最中なので、専門の方とはまた違った感想を持ち、初学者目線で紹介できると思うので、最後まで読んでいただけるとありがたいです。
基礎から鍛える量子力学
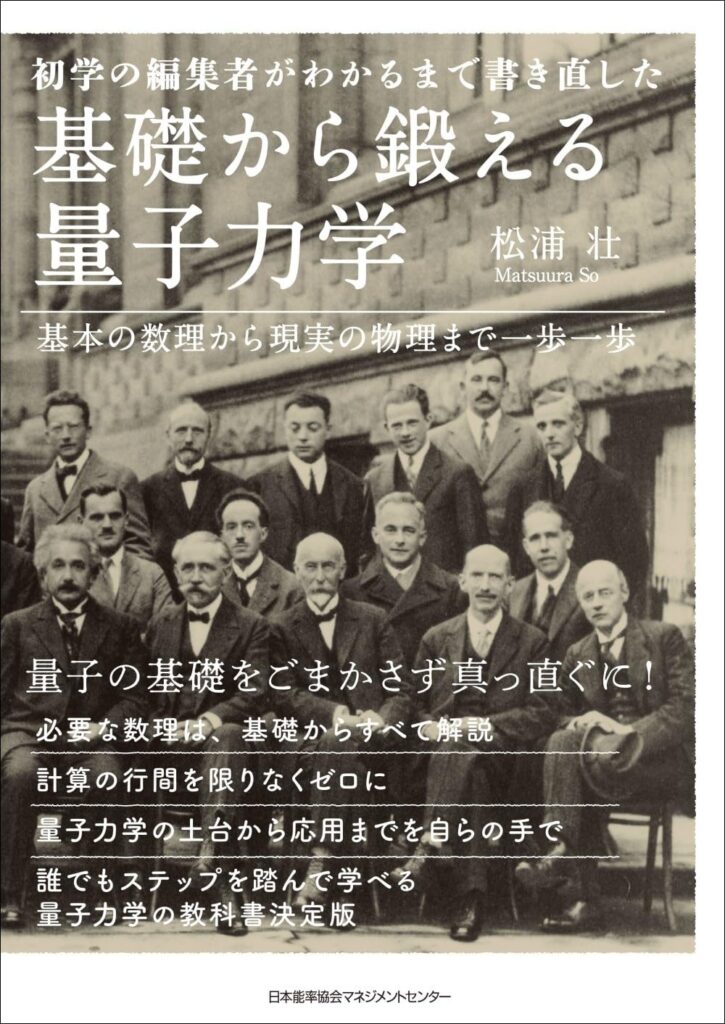
まずはこの本です。本の副題に「初学の編集者がわかるまで書き直した」「基本の数理から現実の物理まで一歩一歩」とあるように、微分積分など、数学の本当の基礎の部分から分かりやすく書かれています。そのため、途中で置いて行かれることなく量子力学を学ぶことができます。
所々にある練習問題も、その章を理解するのにとても役立ちます。この本をやることで基礎を鍛え、次に取り組むより難しい一冊へと滑らかに接続できるようになると思います。
線形代数と量子力学
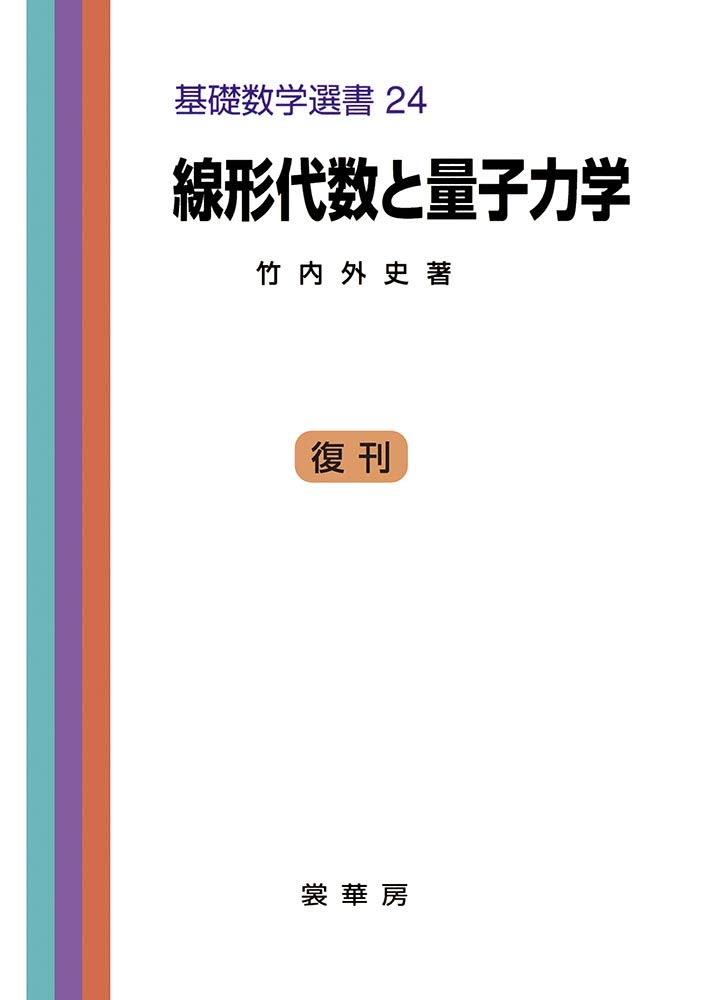
量子力学における行列力学とは、文字通り行列によって物理現象を解明する手法です。もちろん線形代数の知識や技がフルに用いられています。そのため、量子力学を学ぶ際に線形代数は不可欠なのです。
この本では、高校レベルの前提知識で、QMを学ぶに必要な線形代数の知識が得られます。
筆者自身も、この本で線形代数を学ぶまでは、
「量子力学って、なんか行列の機械的な計算ばっかだな~」
と思って、正直あまり楽しんで学べていませんでした。
この本で線形代数を学ぶことで、量子力学における数学的操作の物理的意味がとても良くわかるようになると思います。
現代の量子力学 上 (JJサクライ)
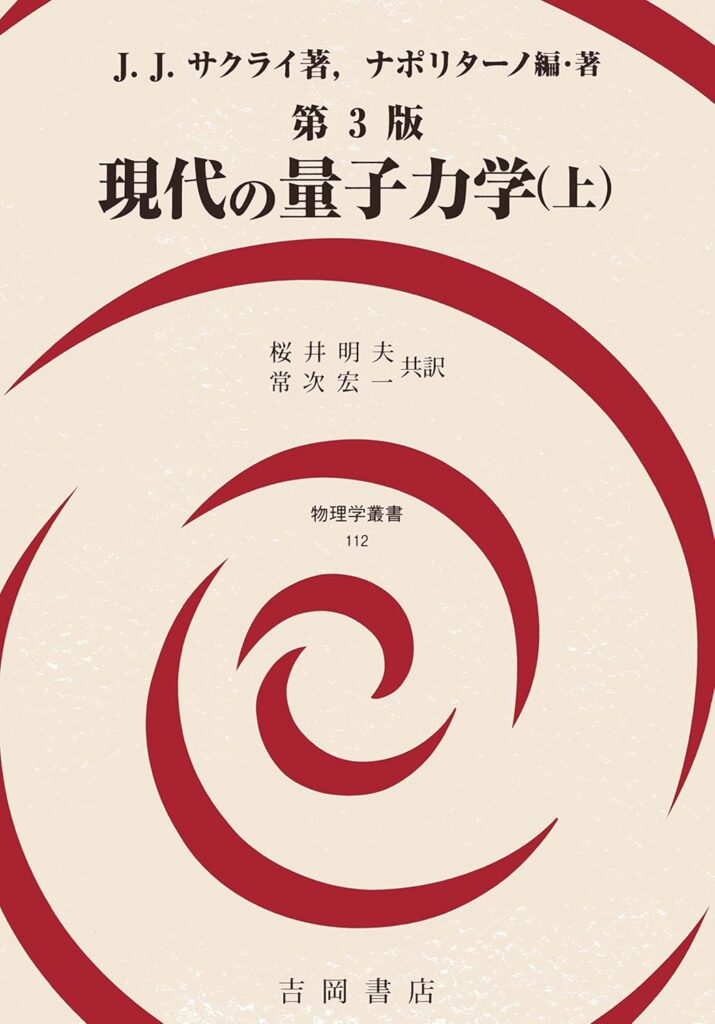
海外の大学でも広く用いられている教科書です。
第一章で、量子状態を記述する際にとても便利な記法であるブラ・ケット記法についてとても分かりやすくまとめてあります。正直、このブラ・ケット記法を学ぶためだけに読んでもいいほど分かりやすいです。
二章以降はとても難しいです。
量子力学 I (朝永振一郎)

この本は、量子力学を歴史的に解明しており、「どのようにしてこの不思議な学問分野が生まれたのか?」「どのようにして組み上げられていったのか?」といった量子力学の"こころ"を知ることができます。
